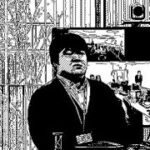大谷翔平選手の電撃結婚ニュースが報じられた。他人事ながら本当に喜ばしいことだ。TWSも明日3月2日(土)、9日(土)続々と社員の結婚式が控えており、私も晴れ舞台に招待されている。結婚して子どもが生まれて家族が増えてマイホームを購入する。そんな社員や社員の家族が増えてくると社長のモチベーションも上がるものだ!今日は、都立高校入学試験の発表日でもある。社員の子どもたちも発表を控えているが、私の子ども達も昔そうだったように、同じくドキドキしていた親の立場を思い出す。果たして、昨今の物価上昇に給料アップ額が追い付いていくだろうか!?日経平均株価がバブル期を超えて史上最高値だと言われているが、果たして皆は実感があるだろうか!?果たして利益を出すだけで会社は幸せだろうか!?答えはNOだと思う。仕事のやりがいであったり、人間味がある会社を目指しつつ利益を出し、地域や関わりある周囲の人達に、必要とされる会社にならなければ生き残れないだろう。TWSファミリーとして社員と社員の家族が皆、そして来月には新卒社員も入社してくる。『この会社に入って良かった』と心から思ってくれる社員がたくさん集結する笑顔ある会社へ、もっともっと目指していきたい。
- 2024/03/01