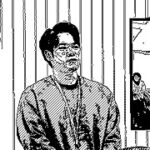5、6年前から流行しているため知っている人も多いと思うが、私はVirtual Youtuberの動画での配信を見るのが好きだ。Vtuber等とも呼ばれ、近年では動画配信に加え、ラジオやテレビによるメディアへの露出も増加している。そもそもVirtual Youtuberとは、キャラクターを用いて動画投稿や生放送を行う配信者のことを言うが、元々は初めてVirtualでの動画配信を行った人物を指す言葉であったそうだ。私はそのVirtual Youtuberのライブに行くのが趣味なのだが、初めてライブに参加したのは4年前。友人に急遽、前日に誘われて参加し、当時は会場はキャパが1,000人ほどのライブハウスで、スクリーンに投影されていただけだったが想定以上に楽しめた。地下アイドルやインディーズ時代のアーティストが埋める位のキャパで行われていたが既にその際も満員状態であった。昨年の夏にはVirtual Youtuberで初となる日本武道館で開催され、7000人ものファンが熱狂したそうだ。また、AR技術の発展によりライブパフォーマンスも格段に上がっており、従来のスクリーンに映し出された平面的な映像を見るだけでなく、正にそこに実物がいるかのように立体的に映し出されたり、実物の人間との共演等の演出が素晴らしい。単なるYoutubeの動画として見るだけでなく、映像技術や魅せ方等、これからもVirtual Youtuberの動向から目が離せない。
- 2023/01/20