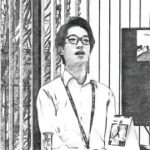最近知って、少し驚いたことがある。メールセキュリティにおける「PPAP方式」についてだ。PPAP方式とは、パスワード付きZIPファイルをメールで送り、後から別メールでパスワードを通知する方法を指す。一見すると安全性を高める合理的な仕組みに思えるが、実は課題も多い。第一にファイルとパスワードが同じメール経路を通るため、通信が傍受された場合には両方を取得される可能性がある。第二にZIPが暗号化されていることで、受信側のセキュリティソフトが内部を検査できず、かえってマルウェア感染のリスクを高める恐れがある。実際、2020年には内閣府・内閣官房において、同経路でZIPとパスワードを扱う運用を見直す方針が示された。現在は、クラウドストレージを用いてアクセス制限や有効期限を設定し、安全に共有する方法が推奨されている。今回の件を通して、慣習が常に最適とは限らないことを学んだ。これからも「本当に意味があるのか」という視点を持ち続けたい。
- 2026/02/26