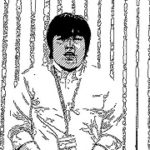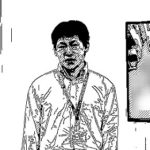先日、友人から届いた郵便物を確認すると、謎解きゲームと封筒が入ってた。この謎解きは、今のご時世に合わせビデオ通話を利用してステイホームでもできるというコンセプトで作られていた。私と友人は別々の封筒を持っており、その中にお題が記載され、共通のお題や時にはそれぞれ異なるお題を解いていった。中には相手の状況を想像しながら答えていかなければならない内容があったりとそれぞれが離れているからこそ楽しめるようになっていた。この謎解きは、芸人のサバンナ高橋さんがプロデュースしており、リモート会議のみで作り上げたものだとのこと。リモートワークでも今までと変わらない、またはそれ以上のものを作り出せるのだ。私も3月4月と在宅勤務で業務を行い、特にeRIMSの保守対応では通常何時間もかけて訪問して対応しているところ、テレビ電話でお客様に操作してもらい、作業を完了する事ができた。訪問できないことがデメリットに思っていたが、逆に丁寧な説明をすることで満足して頂けた。緊急事態宣言が明けて今までのような生活に戻りつつあるが完全には戻らないだろう。そんな中でも今までと違うからと嘆くのではなく、今までと違う環境を活かして今までにない価値を創造したり、付加価値を提供して満足度を高めていく行動が必要であると改めて感じた。
- 2020/06/02