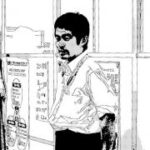2018.09.07(Fri) A・Aテクニカルエキスパート(♀)
長い休日のあとや月曜の朝に憂鬱を感じる現代人が多いと幸福学者が論じていた。
これを軽減する方法も一緒に3つ提言されていた。
1つ目は休日にも平日と同じ時間帯に予定を入れて、平日と同じリズムを刻むこと。
その時、休日の予定には体を動かすもの、知的好奇心を満たすものでバランスを取ると良い。
幸福を感じている人はこのバランスが上手く取れているそうだ。
2つ目は、月曜日の午前中の予定だけを紙に書き出して脳を整理すること。
3つ目はマインドフル・イーティングと呼ばれる味覚を使った簡単な瞑想で、コーヒーの苦味やドライフルーツの甘みなどの感覚に集中することで、一度気持ちを切り替え脳をリフレッシュすることだ。
日々のちょっとした工夫で憂鬱感は減らすことが出来るようなので、ぜひ試してみたい。
充実した休日を送れば、更に精力的に平日の業務が送れるのではないだろうか。