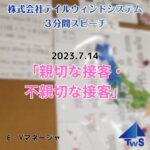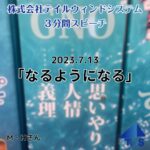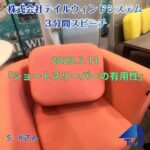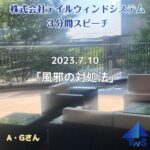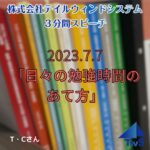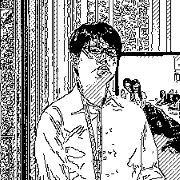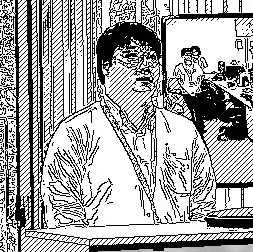先週の休みの日に布団を干していたところ、強風でかけ布団が下に落ちてしまい、家の下にあるお店の屋根に引っかかってしまった。その際、お店の方に許可をいただき物干し竿を使ってなんとか取ろうとしていたが、なかなか取れずに苦戦していた。すると、それを見ていた通りがかりの方が「大丈夫ですか?」と声をかけてくれ、布団を取るのを手伝ってくれた。そのお陰で、無事に取ることが出来た。私はその方が声をかけて助けてくれたことに対して感動した。そして、これが逆の立場だったらと考えたとき、私は声をかけて助けようとしたかを考えてみたが、多分助けていなかっただろうと思った。声をかけて不審がられないか、怖い人だったらどうしようなどと考えてみたが、行動できなかったと思う。先日、全社員で受講したボランティア研修後のアンケートで、私は「オストメイトの方が困っているのを見た際は積極的に声をかけたいと思う」という回答をした。しかし、今回の自分のように困っている人を見たときに声をかけられるようでなければ、いきなり実行することはできないはずだ。何事も実践を重ねることで慣れていくものであり、まずは小さいことでも人に親切にしていきたい。そして助けることに慣れていくことで、より多くの助けを必要としている人たちの役に立ちたいと思う。