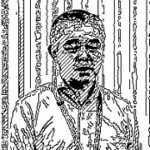リモートで仕事をする機会が増えたことにより、時間の使い方が変わった。通勤時間で使用していた往復2時間と、身支度にかかる30分で約2時間半ほどの余裕ができたため、家の片づけに時間を使うことにした。はじめは朝のちょっとした時間で何が出来るのだろうと思っていたが、1時間みっちり片づけをしたところ、すっかり家の中がきれいになることに気付いた。そのまま2週間ほど続けていたのだが、続けているうちにドンドンとその時間が短くなってしまい、最終的には行わない日も出てきてしまった。そんな中、体操の内村航平選手のインタビューを聞く機会があった。オリンピックで期待されていた中で失敗をしてしまい数日間落ち込んでいたという話だったのだが、では復活できた理由は何かというと「落ち込んでいる自分、弱い自分に飽きたから」と仰っていた。私は今まで、“飽きる”や“三日坊主”という言葉には悪い印象しか持っておらず、良い意味での“飽きる”や“三日坊主”という使い方が新鮮に感じた。ポジティブになれるようなことは毎日続けることで身につけて習慣化し、逆にネガティブな内容は積極的に三日坊主にして、変わろうという意識を持つことが大事だ。