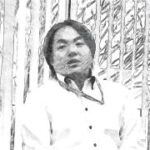最近、仕事上で「成長とは何か」について考えることが多い。一般に成長とは、知識が増えることや、できることが多くなることを指す場合が多い。もちろんそれも成長の一つである。しかし、私はもう少し違った視点で成長を捉えている。誰しもが幼少期においては、何もわからず、何も経験していない。そのため、日々さまざまなことに挑戦する。挑戦し、失敗し、それを乗り越えることでできることが増え、それが喜びとなり、次の挑戦へとつながっていく。人はこのような成長のサイクルの中に、自然と身を置いているのである。しかし、年齢を重ねるにつれて、わかることが増え、経験も積み重なっていくと、新しいことに挑戦する機会は次第に減り、困難を乗り越える喜びを感じにくくなる。そして、ある時点で人は成長することをやめてしまうのではないか、と感じている。仕事においても同様である。同じことを長く続けている人と、やったことのないことに挑戦し、時には失敗を経験している人がいるとした場合、どちらが成長していると言えるだろうか。私は、たとえ失敗したとしても挑戦し続けている人の方が、人として成長していると考えている。そして、そのような人を、これからも応援していきたい。